フィールドから採ってきた雑穀でパンみたいなものは作れるだろうし、豆も採れるだろう
藤岡要さんが異文化の設計をする時に出てきた発想
――禁足地に住む人々の異文化感もよく表現されていると感じました。苦労された点や,見てほしい点などありますか。
藤岡氏:
今回は当初から「人も生態系の一部として描きたい」というコンセプトがありました。禁足地にはハンターがいないので,環境が変化するなかでモンスターと人がどう対応しているかをかなり細かく設定しました。
それは異文化を描くことであり,挨拶や座り方といった基本的な部分を考えるところからのスタートでした。食生活ひとつをとっても「農耕できない環境で何を食べているんだろうか?」「フィールドから採ってきた雑穀でパンみたいなものは作れるだろうし,豆も採れるだろう」「家畜は飼えるんじゃないか?」「それなら乳でチーズも作ってるんじゃないだろうか」……といった風に設計にかなりの時間を使いました。
ハンターが乗るセクレトにしても,しっかりとした設定が必要でしたし,ゲームとしてやりたいことが出てきたら出てきただけ設定を考えないといけない。苦労はしましたが,その甲斐あって,異文化にハンターたちが入って交流していくさまがきちんと表現できたように思います。
農耕をナメてるとしか思えない
一応古代オリエント博物館によると、テル・ルメイラ遺跡(中東シリアのどこか)周辺には雨季の間に自生した麦を採取する生活が現代まで続いているらしい。
さすがに自主栽培もしてるけど
人間が栽培する前(原種)はいずれも実が小さい・収穫量が少ない・味が悪いなど質が低く我々が普段目にする食用に適した植物は自然界にほとんどない。
通常の人類史であれば採取狩猟生活(数百万年)を経て農耕→畜産となるのだが…狩猟と農耕をすっ飛ばして採取→畜産は何を想定したリアリティなんだろうか。
踏み込んだ話
| 長くなるので折り畳み |
採取狩猟生活では前述の通りの質の悪い収穫物を探して回る質素な生活になるため、
「作物が育てられない厳しい土地に住み、家畜に頼って生きる民」というものを出したかったんだろうに、 |
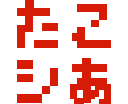 たこシあメモリアル
たこシあメモリアル